家飲みでは、お店で飲んだ日本酒や酒蔵や酒店で買った全国の美味しい地酒を厳選して紹介します。
今回は静岡県静岡市の三和酒造が醸す『臥龍梅 純米吟醸』を飲んだ感想を紹介します。
三和酒造 臥龍梅の由来
三和酒造の成り立ち
三和酒造という会社名が示すとおり、1971年(昭和46年)旧清水市内(現静岡市清水区)の「鶯宿梅酒造」、「小泉本家」、「清水酒造」の蔵元が合併して誕生しました。
久しく合併前に各社が使用していた銘柄を使用していて、地元では「静ごころ」という銘柄で、市内唯一(旧清水市時代)の地酒として消費者の皆様から愛されております。
地元を流れる清流興津川の良水を使って仕込まれます。
市川商店 参照
臥龍梅の由来
「臥龍」という言葉は古く、「三国志演義」です。
魏、蜀、呉、「劉備玄徳(りゅうびげんとく)」が在野の賢人「諸葛孔明(しょかつこうめい)」を三顧の礼をもって自軍に迎え入れる下りに「臥龍・鳳雛 がりょう・ほうすう」という言葉があります。
「臥龍」は寝ている龍、まだ雲雨を得ないため天にのぼれず、地にひそみ隠れている龍のことで、転じて、まだ志をのばす機会を得ないで民間にひそみ隠れている英雄、「諸葛孔明」の例えであります。
わが国に移り戦国時代末期のことです。後に徳川幕府を開設した徳川家康は、幼少の一時期、今川家の人質として当社の近隣の「清見寺 せいけんじ」という禅寺に暮らしていました。
そしてその無聊の徒然に、寺の庭の一隅に一枝の梅を接木したと伝えられています。
「諸葛孔明」の故事どおり、「清見寺」にあった頃の家康は地にひそみ隠れておりましたが、その後、龍が天にのぼるがごとく天下人となりました。
家康の植えた梅は三百年の月日を経て大木に成長し、さながら龍が臥したような見事な枝振りもあいまってか、この梅は何時の頃からか「臥龍梅」と呼ばれるようになりました。
「臥龍」の故事に習い、やがては天下の美酒と謳われることを願って新しく発売するお酒を「臥龍梅」と命名いたしました。
三和酒造サイト 抜粋
臥龍梅 純米吟醸
臥龍梅は2002年に発売された新ブランドです。
総米660キロの吟醸小仕込みを基本とし、大吟醸はすべて袋吊り。米の種類と精米歩合のみという、極めてぜいたくなつくりの日本酒です。
静岡県ではこのブログで紹介した「開運」や「磯自慢」など多くの酒蔵が「静岡酵母」を用い、「静岡吟醸」と称されるすっきりとした爽涼な特徴があります。
臥龍梅のその最大の特徴は、その静岡酵母を使っていないことです。
静岡の酒で静岡酵母を使わないことはかなり異端でしたが、県内最後発のブランドだったため、他との差別化の為、あえて同じ酒質にしなかった経緯があります。
一般的に、東北や北陸などの寒い地方では、もろみが低温でゆっくり発酵するので、味が乗った濃い酒になる。一方、暖かい気候の静岡では、アルコール発酵が早く進むため、味が乗りにくい特性があります。
静岡酵母は酸が出にくい特性があるため、いっそうサラリとした軽い味わいになります。
臥龍梅は味も香りも豊かでインパクトがあり、後口のきれいなお酒です。
今回飲んだ純米吟醸は華やかな香りと白ワインを思わせるフルーティーな酸味が特徴的でした。

| 名称 | 臥龍梅 純米吟醸 |
| 商品説明 | この「誉富士」は静岡県が新たに開発した酒造好適米で静岡県内においてこちらの三和酒造様が一番最初に仕入れて仕込み、市場に初めてお披露目をしたお酒で、県内はもちろん全国でも話題になりました。 |
| 容量 | 720ml |
| 原材料 | 麹米: 掛米: 静岡県産誉富士 |
| 精米付合 | 精米歩合55% |
| アルコール度 | 15度 |
| お召し上がり方 | 冷酒 |
時代が流れインターネットで多くの情報を手に入れれる様になりました。
美味しい日本酒を飲んで楽しい時間を過ごすのであれば、作りての物語も一緒に味わう様になりました。
| 三和酒造株式会社 | 住所 静岡県静岡市清水区西久保501-10 |
| 酒 銘 | 臥龍梅 |
| ホームページ | http://www.garyubai.com/ |
| 創業年 | 1686年 |
にほんブログ村

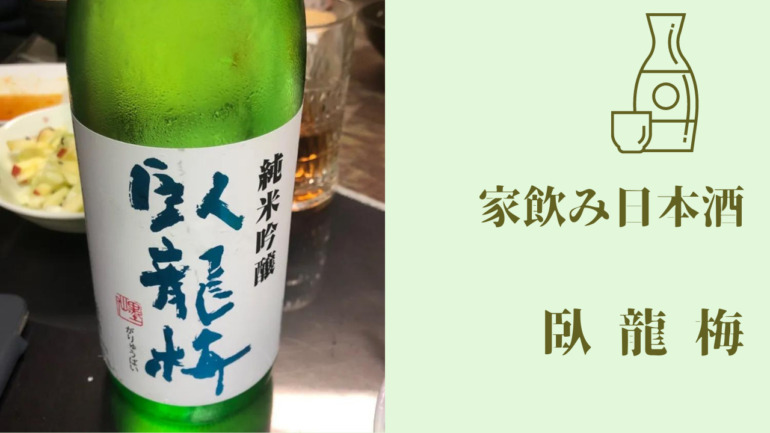


コメント