LISTEN /ケイト・マーフィー/ 日経BP
この お勧め本紹介を通じて本を読むことの楽しさや色々な価値観を知り、成長に繋がることを紹介したいと思っています。
今回はビジネス書分野で多く出版されている傾聴「聴くこと」について500ページにもわたり事例を交え紹介されている本です。
著者のケイト・マーフィはヒューストンを拠点に活動するジャーナリストです。ニューヨーク・タイムズ、ウォール・ストリート・ジャーナルなどで多くの人にインタビューしてきた聞くことの達人です。
読み進める中で以下のようなダメな聞き手行動についての指摘も、ついつい行ってしまっている自分と照らし合わせてみたりもします。
- 話をさえぎる
- いま言われたことに対して、あいまいだったり、筋が通らない反応をする。
- 携帯電話や時計、部屋の他の場所など話して以外を見る。
- 落ちつきがない。
このようなダメな聞き手をやめただけでは、優れた聞き手になれない理由の多くを本編で多く紹介されています。
「話を聞かれない」と孤独になる
この本のプロローグで衝撃的なエピソードが紹介されています。
現在のZ世代を中心にSNSなどを通じてより多くの人と関わっている現状の中、アメリカにおいて、孤独を感じたり、うつ状態の人が年々増加している様です。
話を聞いてもらえないと、人は孤独になり、心理学や社会学の研究者は、アメリカで孤独がまん延していると警告出しています。
その中でも、現在の孤独のまん延について最初に警鐘を鳴らしたのはチャットルームの投稿は驚きでした。
2004年、あまり知られていないチャットルームにこんな投稿をした匿名の人物だった。
「さみしい。誰か話しかけてくれないか?」彼の心の叫びは拡散され、メディアも報道した。
こうした投稿の中には「毎日たくさんの人に囲まれているけれど、まったくつながりを感じられない」と悩む人が多数いる様です。
孤独な人たちは、自分の考えや感情を話す相手がいません。
そして、切実なのは、考えや感情を聞かせてくれる人もいません。
最初に投稿した人は誰かに話したかったのではなく、誰かの話を聞きたいと切望していたのです。
この投稿以来、孤立や孤独を感じている人の数は増えいます。
2018年にアメリカ人2万人を対象に行った調査では、顔を合わせての深いやりとりを日頃していないと答えた人は、半数近くに上った。
1980年代に行われた類似の調査では、わずか20%しかいなかったのに驚きです。
「聴く」ことは自分自身への理解も深めてくれる
テクノロジーが進化した今の時代になぜ聞くスキルを伸ばす必要があるか疑問に思う人も多くいると思われますが著者は聞く行為が人生を生きる上でもっとも重要と言います。
「聴く」ことは自分自身の理解と話し相手への理解も深め、この能力は生まれる前の胎児の頃から音に反応し、妊娠後期には、人の声とそれ以外の音を聞き分けられる能力を身に付けています。
また、人が死ぬ間際に最後まで持ち続ける感覚のひとでもあります。
後天的に聴力を失った人は、情緒面・認知面・行動面においても影響があることが幅広い研究で示されています。
CIAが採用するのは、聞く力が優れている人
アメリアのCIAは局員の聞く能力を伸ばす訓練をするよりも、もともと聞き手として優れた人を採用します。
いちばん優秀な聞き手を取り調べと諜報活動に配置されます。
CIAでは傾聴は、再現可能な科学とうよりアートであると考えてます。
聞き方のテクニック
よくビジネス書で書かれたいる以下のような方法論について著者は否定的です。
- アイコンタクトをする。
- うなずく
- ところどころ「そうだね」と入れる。
- 相手が話し終えたら言葉を繰り返す。
- 言い換えたりして確認する。
- 聞き手である自分はここまでまってから、話始める。
この方法を実践すれば、自分が欲しいものが手に入る(つまりデートする、売上を上げる、最善条件を交渉する、企業の出世階段を上がる)という前提があるかれです。
確かに傾聴はこれらの目的達成の一助となるかもしれません。
しかし、それがあなたにとって人の話を聞く唯一の動機であれば、それは聞いているふりをしているにすぎず、相手はすぐに気づくでしょう。
もし本当に相手の話を聞いているのなら、そんなふりをする必要はありません。
聞くという行為には、何よりも好奇心が必要です。
本書 抜粋
テクニックにだけはしると本当の意味での傾聴はできないという本質が書かれています。
この本のアマゾンの紹介には一生の友人をつくり,孤独ではなくなる方法を教えると紹介されています。
本書の冒頭部分では、テクノロジーが発展しSNSなど人とつながる機会が多くなっているにも関わらず、心の病や孤独を感じる人が増えている現状を紹介されています。
テクニックでない好奇心からの傾聴で豊な人生が送れるエッセンスが含まれています。
興味深い本なのでお勧めします。

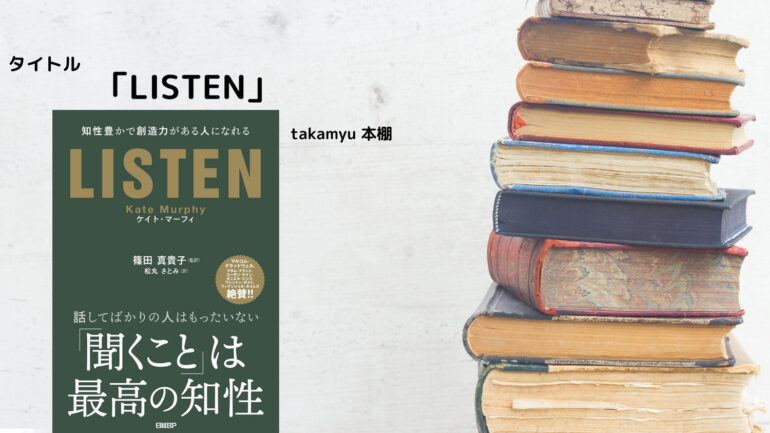


コメント